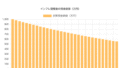「米国株に投資しているけど、円安で得してるのか損してるのか分からない」「為替の動きで資産が目減りするのが不安」──こんな声をよく聞きます。この記事では、長期投資家が為替リスクにどう備えるべきか、どの通貨で資産を保有すべきかを整理してお伝えします。
資産運用といえば「株式や債券への投資」が真っ先に思い浮かびますが、意外と見落とされがちなのが「通貨リスク」への対応です。
特に日本国内で生活していると、日本円で給料をもらい、日本円で貯金し、円建ての資産だけを保有しがちです。
しかしこれは言い換えれば「日本という一国の通貨に資産を全ベットしている」状態。日本で教育を受け、日本で就職している時点で、日本円のキャッシュフローは十分潤沢に得ることができる環境にあります。
この記事では、為替リスクの基本から外貨分散の重要性まで、長期投資家の視点でロジカルに解説します。
円だけの貯金=通貨リスクにさらされている状態
為替は基本的に「需要と供給」で決まります。日本円を売ってドルを買う人が多くなれば円安に、逆にドルを売って円を買う人が多ければ円高に動きます。
たとえば、私たちがNetflixやApple Musicといった米国企業のサービスを日本円で利用すると、企業はそれをドルに換えて米国本社へ送金します。これは実質的に「円売り・ドル買い」となり、円安要因になります。
一方で、トヨタやホンダのような日本企業が自動車を米国に輸出し、代金をドルで受け取って円に換える場合は、「ドル売り・円買い」になるため、円高圧力がかかります。
また、最近ではNISA制度の拡充により、個人が外国株や米国ETFを購入する動きが活発になっています。これは日本円で外貨建て資産を買うことになるため、構造的に「円売り・外貨買い」のキャピタルフライト(資本流出)を生む要因になります。
税制優遇が後押しする形で、国民の外貨資産保有が進むほど、円安圧力は高まりやすくなるという側面も無視できません。
日本円は「安全通貨」と呼ばれることもありますが、過去の為替レートを見ると一貫した上昇トレンドはなく、むしろ長期的に見ると円安傾向にあります。
たとえば、1995年には1ドル=80円台まで円高が進みましたが、2025年現在では1ドル=150円前後を記録する場面もあるなど、実に2倍近い差があります。
このような為替の動きは、旅行や輸入品の価格だけでなく、外貨建て資産の価値にも大きく影響します。
円だけで資産を保有していることは、実は見えにくいリスクを抱えているのです。
また、少子高齢化や財政赤字といった日本の構造的課題を考慮すると、今後の日本円の価値が将来も安泰とは限りません。
通貨も資産の一部。外貨を使った分散戦略とは
資産運用において「分散」は基本中の基本です。株式だけでなく、債券、不動産、そして「通貨」もまた、分散対象と考えるべきです。
外貨預金という形もありますが、投資信託やETF(たとえばVTやVTIなどの米国上場ETF)を通じて外貨建て資産に投資することで、為替と株価の両方を分散することが可能です。
特に、全世界株式インデックスファンド(eMAXIS Slim 全世界株式など)は、通貨分散の効果も自動的に組み込まれているため、初心者にもおすすめできます。
実際、外貨を意識していなくても、これらの商品を通じて自然と外貨に資産を置くことができます。
さらに、為替ヘッジを行わないファンドであれば、為替の変動をそのまま享受できます。これにより、円安時には為替益も得られるなどのメリットがあります。
為替の動きは読めない。タイミングを狙わない長期戦略
株式市場は長期的に右肩上がりの成長を見せていますが、為替市場はそうではありません。
実際、過去数十年のドル円チャートを見ると、円高・円安を繰り返しているだけで、はっきりとしたトレンドがあるわけではありません。ニュースやSNSでも、為替を予想するような内容もありますが、個人的には全く当てにしていません。
このような動きの予測は非常に難しく、短期的に「円高だから買い」「円安だから売り」といった戦略はうまく機能しないことが多いです。
そのため、為替のタイミングを狙うのではなく、コツコツと外貨建て資産を積み立てていくことが、現実的かつ再現性の高い戦略となります。
実際に筆者も、特定の為替レートを意識せず、毎月一定額を国際分散型ファンドに積み立てています。
為替が上がればその分の為替益があり、下がれば安く多く買えると考えることで、心理的にも安定した運用が可能になります。
まとめ:円安に備えるのではなく、円依存から脱却する
為替リスクは恐れるべきものではなく、適切に付き合っていくべきものです。
株式や債券と同じように、通貨もまた分散する対象です。
日本円に偏った資産配分を見直し、外貨建て資産を取り入れることで、より安定した資産形成が可能になります。
円安になってから慌てて外貨を買うのではなく、日ごろから円に偏らない資産構成を意識することで、為替変動にも動じない投資姿勢が育ちます。
「為替を読む」のではなく、「通貨を分散する」。その視点が、長期投資家にとっての鍵となるはずです。