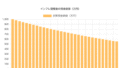「物価高が止まらない」時代
最近、スーパーでの購入金額が高くなったと感じたことはありませんか?
これは一時的な物価高ではなく、日本の経済システム全体が「インフレ・モード」に移行している証だと思っています。日本でもエネルギー価格や食料品価格の上昇が続いており、生活コストがじわじわと家計を圧迫しています。
物価高による家計圧迫は誰にとっても負担感がありますが、特に危険にさらされるのが「リタイア世代」です。
現役世代にはインフレが有利になりうる理由
働いて稼ぐ力がある
現役世代には、資産を切り崩すのではなく「増やす」力があります。
- 昇給や転職で名目賃金の上昇が期待できる
- 副業や投資など、インフレに耐性のある戦略を取れる
- スキルアップにより、インフレ以上の収入成長も可能
- インフレに強い資産を持つリスクが取れる
物価上昇があっても、それに見合う収入を得られる環境があれば、インフレはむしろチャンスにもなりえます。
借金の実質負担が軽くなる
住宅ローンや奨学金など、長期の借入がある現役世代にとって、インフレは「借金の実質的な目減り」を意味します。
物価が上がる=お金の価値が下がる → 将来返すお金の「実質価値」が下がる、という構造です。
引退世代にインフレが不利な理由
年金は物価に完全には連動しない
公的年金は「マクロ経済スライド」によって物価や賃金と連動する仕組みがありますが、完全なインフレ追従ではありません。
たとえば物価が5%上がっても、年金額が同率で上がるとは限らず、実質的な目減りが起こります。
資産を増やす手段を失っている
引退後は、原則として給与収入がなくなり、投資で大きなリスクを取るのも難しくなります。
- 現金や預金に偏った資産構成では、インフレに無防備
- 株や不動産を積極的に買い増す余裕もない
この状態で物価だけが上がると、「資産の実質価値が削られる」結果になります。
支出は減らせないのに増える
高齢になると、医療費・介護費・光熱費などの支出は増えがちです。
可処分所得が減る一方で、必要不可欠な支出が増えるため、生活の厳しさは加速します。
シミュレーション:インフレで生活はどう変わるか?
以下は、現役世代とリタイア世代の家計に、インフレがどのような影響を及ぼすかのシンプルな比較です。
| 項目 | 現役世代(40歳) | リタイア世代(70歳) |
|---|---|---|
| 年収 | 600万円(会社員) | 年金180万円(15万円/月) |
| 資産構成 | 現金200万円+投資800万円+住宅ローン残あり | 現金2,000万円(ほぼ預金) |
| インフレ率 | 毎年2% | |
| 5年後の実質的影響 | ・給与上昇と副収入で収入増も期待可 ・投資収益がインフレと連動すれば資産も成長 ・固定金利の場合はローンの実質負担は軽減 |
・預金の実質価値が約9.6%目減り(2000万→約1808万円相当) ・年金の増加は物価に追いつかず、生活水準が低下 ・医療費・光熱費などの支出増に対応しづらい |
このように、同じインフレ2%でも、影響の質が大きく異なります。
結論:インフレに強いのは「資産」と「稼ぐ力」を持った人
インフレに耐えられる人とそうでない人の違いは、次の2つに集約されます。
- 現金ではなく「モノの価値を保てる資産」
- 働いて増やせる「稼ぐ能力」
これらを持たない人ほど、「資産の目減り」と「生活負担の増大」というダブルパンチを受けることになります。
引退するにあたり、「現金主義」や「年金主義」は、すでに時代遅れの危険な思想になりつつあります。
資産を持つこと。稼ぐ能力を持続すること。
それこそが、インフレという経済の荒波に耐えるための、長期的な守りになるのです。
あとがき:あなたは備えられていますか?
インフレは止められなくても、備えることはできます。
あなたは、“稼ぐ力”と“守る資産”を、もう持ち始めていますか?