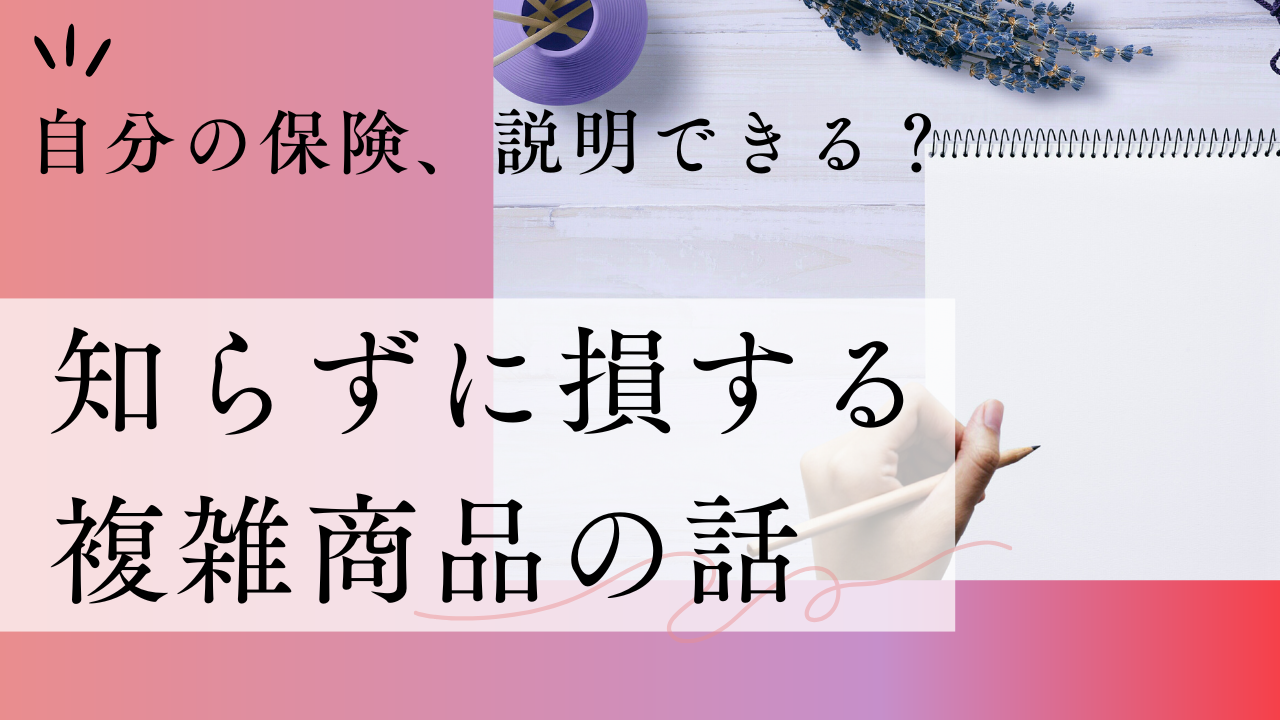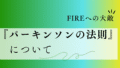FIREや資産形成を目指す人にとって、「保険」と「投資」はどちらも重要なテーマです。ですが最近は、この二つを組み合わせたような“複雑な金融商品”が増えています。変額保険や外貨建ての貯蓄型保険など、一見お得そうに見えるこれらの商品、本当に内容を理解した上で契約していますか?
この記事では、手数料が不透明で複雑な保険商品がなぜおすすめできないのか、そして私たちユーザーがどう判断すべきかを理系的な視点で考えていきます。
はじめに|その保険、本当に理解していますか?
「この保険、利回りがいいんですよ」
「外貨建てだから将来有利ですよ」
「保障もついて、投資もできる、一石二鳥です」
このようなセールストークに出会ったことはありませんか?しかし、その保険にかかる手数料はいくらか、契約途中でやめたらどれだけ損をするか、明確に説明できる人は多くありません。
仕組みが複雑になればなるほど「なんとなく良さそう」で契約してしまい、後から「こんなはずじゃなかった」と後悔するリスクが高まります。
ありがちな“よくわからない保険”の例
変額保険
保険料の一部が投資信託で運用され、運用結果によって受け取る金額が変動します。
外貨建て保険(ドル建てなど)
為替レートの影響を受けるため、円安・円高で受取額が大きく変わります。
貯蓄型保険
保険というより“長期積立”に近い設計で、途中解約すると元本割れすることがほとんどです。
学資保険
教育費を貯める目的で加入するものの、利回り・手数料構造が見えにくい商品が多いです。
これらの商品に共通するのは、「保障」「投資」「為替」が混在しているという点です。
なぜ複雑な保険は避けるべきなのか?
手数料がブラックボックス
契約時・運用時・解約時に複数の手数料がかかりますが、説明資料だけでは分かりにくいことが多いです。
「保険」「投資」「為替」がごちゃ混ぜ
本来別々に管理すべきリスクが一つの契約にまとめられており、自分で判断しにくくなります。
長期拘束と中途解約リスク
10年・20年単位での契約が多く、途中でやめると大きく元本割れするケースが多いです。
提供者に都合がいい構造
販売手数料・為替手数料・運用管理費など、金融機関にとって“儲かる商品”であることが少なくありません。
ユーザー側の知識がないことを前提にした「複雑さ」は、もはや設計ミスではなく提供者側の“戦略”とも言えます。
シンプルな保険が選ばれる理由
掛け捨ての死亡保険
月額の賭け金に応じて、死亡時に保険金が支払われる。万が一に備えるだけのシンプルな設計。
収入保障保険
一家の大黒柱に万が一があった場合に、毎月定額を給付するタイプ。目的が明確で使いやすい。
これらの保険は「何にいくらかかっているか」が自分で理解しやすいのが大きなメリットです。
投資したいなら投資信託やNISA、iDeCoなど、自分でリスクとコストを把握できる手段を使うほうが合理的です。
本当に良い商品とは何か?
私もサラリーマンの端くれで、ユーザーに向けて商品設計したり、商品説明の資料を作ることも多くあります。その中でつくづく思うのは、そもそも優れたサービスや商品は、仕組みがシンプルで、ユーザーにとって分かりやすく設計されています。iPhoneなんかはシンプルさや万人向けのユーザービリティを意識して設計されているのがよくわかるし、Netflixは解約が簡単でシンプルでユーザーに優しい。国内のサブスクなどで、○○年縛りで途中解約の場合は違約金が発生する、など納得いかない契約を過去にしたことがある人も多いのでは?これは通信回線でも同じで、実は格安SIMの方が大手キャリアより契約が単純で分かりやすいことが多いです。
金融商品も同じで、「わかりやすさ」はユーザーへの敬意だと私は考えています。
契約内容が複雑なまま販売されている時点で、その商品にはどこか提供者本位の設計がある可能性を疑うべきです。
契約前に「これ、自分の言葉で説明できるか?」と問いかけてみてください。それができないなら、やめておくのが賢明です。
まとめ|複雑な商品には立ち止まる勇気を
「わからないからプロに任せる」ではなく、「わからないから契約しない」という判断こそ、これからの時代に必要です。
FIREや資産形成において大切なのは、“自分で理解できるものだけにお金を託す”という姿勢です。
複雑な保険商品に違和感を覚えたあなたは、すでに半歩先を行っています。ぜひその感覚を大切にし、今後もシンプルで本質的な選択をしていきましょう。
関連記事
シンプルな掛け捨て収入保障保険についての記事
👉 ロジカルに選ぶ、子育て世代向け「死亡保険」の最適解について解説